りらファクトリー*ブドウハゼ収穫研修会に参加しました
公開日:
:
りら工房, オーガニックコスメプロジェクト
先日、りらファクトリーで和歌山県林業試験場が主催する「ブドウハゼ収穫調査・研修会」に参加しました。
昨年もお邪魔したチームZENKICHIさんの畑で行われました。
収穫調査を始めてから5年目となる今回が調査の最終年ということもあり、近畿大学文芸学部・生物理工学部の先生と学生さん、鹿児島県のハゼノキ植人さん、ブドウハゼの雑誌記事を書いてくださった写真家兼映画監督さんなど、県内外からブドウハゼに関心を持つ総勢約30名が集まりました。


りらファクトリーでは昨年も参加して収穫作業に慣れてきた人と今回が収穫初体験の人がいましたが、いろんな方と交流しながら、和気あいあいと作業が進みました。
収穫量は昨年よりは多いけど目標値より少なかったようですが、気候変動が激しいこの時代においても樹は順調に生育しており、これからも収穫量は増えていくとのことでした。
収穫作業終了後、おいしいミカンを頂きながら参加した皆さんとブドウハゼの今後についてお話をする場が設けられました。
生物学の視点、民俗学の視点、生産に関する研究者の視点、他の地域でハゼに関わる人の視点、第三者の視点と、様々な角度からブドウハゼのお話を聞くことができ、またりらファクトリーの活動や想いも改めて紹介できました。
どのお話にも共通していたのが「ブドウハゼを通して地域の魅力を高めていく」という方向性で、様々な展望や考えを聞くことができ、ワクワクしたり勇気をいただいた会となりました。

以下、生徒の感想です。
初めてブドウハゼの収穫を体験して、最初は思っていた以上に収穫するのが固くて力が必要だったけど、最後に近づくとコツを掴んで少ない力でたくさんのブドウハゼを収穫できて嬉しかったです。
名前の通り、ブドウみたいにたくさん実がなっていておもしろかったです。
また、たくさんの大人の方と地域活性化や観光化などたくさんのアイデアや意見を交流できる場があり、とてもいいなと思いました。
ブドウハゼを通して私たち高校生もその中に入れているのが他にはあまりない交流だし、一緒に地域活性化や観光化などの目標に向かって力を合わせれているのがこの集まりの魅力だなと感じました。
りらファクトリーの活動は、地域活性化のための活動や商品化など、他の学校では絶対できない、りらだからできていると思います。
今回のようにいろんな人たちとのご縁があって年齢など関係なく集まれる場を大切にし、この方達といろんな交流ができたらいいなと思いました。
そしてりらファクトリーではキノミノリを通して、地域活性化や産業化をもっと進め、いろんな人に広がって知ってもらえたり、影響を与えれるんじゃないかなと思いました。
これからも、もっといろんな人に知ってもらえるよう方法を考えて、頑張りたいです。
(F・K)
今年も脇村さんのハゼ畑で収穫に参加させてもらい、今年は収穫調査の最後の年で去年よりも多くの方がいました。林業試験場の坂口部長、ハゼノキ植人、近畿大学の教授、学生さん、私たちと同じようにハゼの商品を作ろうとしている方など、私たち以外にも若者がいて、こんなに色んな人がハゼに関わっているんだと驚きました。
今年の収穫量は去年から60kg増えたらしく、でも大勢で採ったのでそれほど時間はかからなかった印象でした。畑の木はまだそれほど高くないですが、ハゼの木はこれからもどんどん大きくなって木登りして実を収穫するような木です。
今回は「高いところは無理しなくていいよー」と言っていただいたのですが、もし低木栽培、少なくともあれより少し高いくらいの木におさめることが成功したら、背の高い外国人の方に採ってもらうのもアリなんじゃないかと思いました。
ブドウハゼ収穫は伝統的な和蝋燭の製造に関わる一端で、それはうまく宣伝できれば「収穫する」ということが観光や体験になるんじゃないかな、と実をもぎもぎしながら、皆さんのお話を聞きながら思いました。
また、個人的にはみかんを初めて収穫させてもらって楽しかったです。畑にハゼやみかん以外にも色んな木があって、収穫祭とかできて、キノミノリが売れたりしても面白そうだなと思いました。
今回ブドウハゼ収穫をさせてもらって、去年の公共で「グローバルでインクルーシブ」の話をしたことを思い出しました。もしも国境がなくなり、人やモノ、技術の行き来のハードルが低くなったら、今度は「民族」や「伝統」が失われる恐れがあるのではないか。
ブドウハゼ産業が衰退したのも海外から安いロウが入ってきて伝統的な木蝋「JAPAN WAX」の需要がなくなってしまったからです。
これまで培われてきた伝統的なものが、どうしたら受け継がれてゆけるのか、そういう目線もこれから加えていきたいと思いました。
ブドウハゼ収穫を楽しみにしていたので、参加できてよかったです。ありがとうございました!
(A・T)
ブドウハゼの収穫を体験させていただきました。
私は初めて体験させていただきましたが、いつも蝋の状態や収穫されたハゼばかり見てきたので、木になっていて栽培されているブドウハゼを見るのがとても新鮮でした。それらをひとつひとつ手作業でもぎ取っていく体験がとても貴重なことだなと感じました。
今までは、今後「地域の産業化」を目指すためには機械化をしていくことも重要なのかなと考えていたのですが、木でなっているハゼを取るのは思ったよりも複雑で精密な作業が必要だとわかりました。
なので逆に、収穫作業という『体験』を資源化していくことが必要なのかなと思いました。
ワーホリなどで活かしたり、いちご狩りやぶどう狩りならぬハゼ狩りとして地域に密着させて、観光客や地元の人に愛される行事にしたりしてしけたらいいかと思います。
現地でどなたかも言っておられましたが、収穫体験→蝋作り見学→(体験できそうな工程があれば体験)→お土産に蝋燭やキノミノリ、と言ったようなツアーも成り立ちそうだなとこれからのハゼのポテンシャルにとてもワクワクしています!
また、ハゼの木の管理の意外な難しいところも知ることができました。それは、木が大きくなればなるほど収穫が難しいということです。他の果物でもそうなのかもしれませんが、細かい作業が必要で機械化が難しいハゼだからこそ手作業で取れなくなると困ってしまうということが今回の収穫体験でわかりました。
収穫量を増やすためには木を大きくした方がいいが、収穫できなければ意味がないという農業のジレンマを実際に見ることができたように思います。
今回の体験からたくさんのことを学ばせていただきました。貴重な体験をありがとうございました。
(T・M)
りら創造芸術高等学校HP
関連記事
-

-
モクロウプロジェクト 夏の研修
夏休みを利用して、りらファクトリーのメンバーは大阪府摂津市にある化粧品会社「株式会社大阪エース」と
-
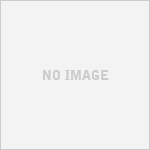
-
オーガニックコスメ製作 【高校生発案の化粧品発売決定】※すでに完売致しました
重大なお知らせがあります!! プロジェクトりらファクトリーが2020年6月から取り組んできた
-
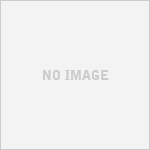
-
ブドウハゼツアーをしました!
5月に、海南市下津地区と有田市でブドウハゼにまつわる場所を訪問しました。 訪れたのは長保寺、チーム
-

-
天然記念物「ブドウハゼの原木」の実の収穫
12月下旬、紀美野町志賀野地区にあるブドウハゼの原木の実の収穫に参加させていただきました。ブドウハ
-

-
オーガニックコスメ製作【⑧精油づくり】
※オーガニックコスメ製作の前回のブログはこちら 10月になり、カヤの実がたくさん集まったとこ
-

-
ブドウハゼ収穫inチームZENKICHI畑
先日、チームZENKICHIの代表である脇村さんの畑で行われた、ブドウハゼ収穫会に参加しました。
-

-
紀美野町で初のブドウハゼ収穫
先日、りらファクトリーでは紀美野町で初めてのブドウハゼ収穫に参加しました! 志賀野さみどり会
-

-
【りらファクトリー】大阪・関西万博で発表
5月15日、16日の二日間、EXPO2025大阪関西万博会場内の関西パビリオン多目的エリアにてりら
-

-
オーガニックコスメ製作【⑤OEM企業探し】
※オーガニックコスメ製作の前回のブログはこちら 4月になり、新たに2021年度が始まったと
りら創造芸術高等学校HP
- PREV
- 第7回りらシアター閉幕
- NEXT
- 【コラム】2024年度 進路速報






